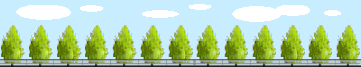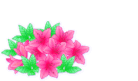森茉莉4 茉莉N・ブルーの風
仙台からの手紙2
わたしが帽子をかぶるのは
明るい陽射しから逃げるためじゃない
もっと明るく世界を染めかえるために
涙の高さよりも少し高く
ささげるようにかぶっているだけ
清水哲男「ブロンディ」
森茉莉の書簡の中に、佐藤家との最初の不協和音が顔をのぞかせ、
さざ波のように不安の影が通り過ぎる。
昭和5年9月8日、杏奴と母しげあての手紙は
しげ、杏奴、類の母子三人が仙台を訪れ、東京に帰って行ったすぐ後のもの。
杏奴に
|
「宿屋へ3人(夫と先妻の子)を呼ぶことは決してしないことにします。」
「又私の家へ皆(母しげ・杏奴・類)を連れて行く日を、 佐藤の留守にした方がいゐと思います。
佐藤がやっと「から」から少し出ても、 その出てゐる苦しさうな変な様子で自分も自由な気持ちになれません。」
「私は「佐藤たちと私」か「お母さんたちと私」でなくては駄目で、 両方が一座しては私は固まったやうな変な気分で苦しくさへあるのです。
「10月の上京では日数も少なく (佐藤家側の)墓参りや方々に義理(の訪問)をする予定のようなので大変悲しい、
これでは(夫と先妻の子と?)4人で出るときは義理(の用事)ということにして、 自分だけの(上京)時に4人(母・茉莉・杏奴・類)で遊ぶようにしなければだめだ」
「自分の小使で(上京)するのをいやとはいはないでせうが、 もしいやといったら、私の境遇をすっかりかへてもらはなくては 承知しないつもりです。」
※( )内は前後の内容から補足
|
久しぶりの家族との再会と別れを経たセンチメンタルな情感の中で、
森家の人びとを前にした夫の態度が影を落とし、
佐藤家の世事の用に対する茉莉の異和が顔をのぞかせる。
後者はやがて次第に輪郭をあらわに拡大していく。
9月19日。母しげから茉莉へ
|
「マリや、馬鹿者には決してかまふものではない。
たとへ毒々しい仇名(あだな)でないにしろ、 こちらからそんな事をしたのはマリの落度だ。
この後は真面目な態度で伯母さんらしくしなくてはいけない。
幸ひにも佐藤の家の子供たちが悪くなくてしあはせだ。」
|
この手紙は茉莉への返信として書かれているが、収録されている
茉莉からしげへの手紙は9月8日の一通だけである。
普通に考えれば、9月8日の茉莉の手紙に対する返信になるのだが・・・
茉莉は9月15日、杏奴に
「お母さんへの手紙で俺がどれだけ勉強家になった事がよく分かったらう」
と記す。
しかし9月8日の手紙を見ても、
それに対応するような文面も、
9月19日の返信でしげが諫めた言葉の強さに相応するほどの内容も、
見当たらない気がする。
森類の回想では「よく母あてに手書きが来た」旨が書かれているが、
他に何らかのやり取りがあったのかもしれない。
いずれにしても母の心配は現実のものとなっていく。
一方で夫の佐藤彰に対しては、その後も 敬愛と信頼を滲ませる。
|
「・・・ヌキ位、ユーモアと、魅力と、凄みを持った人間は少ないね。 大ていユーモアがあれば凄みも魅力もない。花柳ペッシュの如し。
幸蔵はユーモリストで凄いね。 ではまた(チャアリーも、アキラもそうだ)。」
9月25日 茉莉から杏奴へ
|
|
「尊敬すべき人間、田中正平、チャアリー・チャップリン、キキ、佐藤彰。」
「私のアドール(尊敬するものの意)の四人のうち田中正平さんを除いた あとの三人はアドールのド(d)がム(m)になってさヘゐるのだ。」
9月29日 茉莉から杏奴へ
|
収録されている最後の書簡は1月19日、杏奴あて。
新聞に佐藤彰の洋行の記事が出て、茉莉は「今の家庭の状況上、はっと胸が
ふさがれたやうな気がして」
聞き返すが佐藤彰は記事は間違いだと否定する。
懸念する茉莉を納得させるためか、夫は茉莉がクリスマスに大学へ遊びに行った際、
医局の人たちの前で、記事は間違いで行くとしてもずっと後のことだからと明言する。
しかし茉莉は
|
「併し遠からず起こることと覚悟しなければならぬ。 子ども二人をつれて千駄木に別居する事にでもしなければ到底骨と皮ばかりになる。
その時になってそれを彰が承知しなかった場合は絶望です。」
|
この日の手紙では義母から受けた言葉への怒りと嫌悪が激しくストレートに綴られて
終わっているが、そこに記されている姑から嫁への批判も痛烈である。
実弟・森類のいう森茉莉の「先天性主婦失格症」について、最初の結婚のときの
エピソードが幾つか伝えられている。
|
「・・・茉莉姉さんは朝から晩まで使用人から軽く見られている存在であった。 女中たちからは見たこともない馬鹿奥様と思われ、 夫からは、役立たずの不便な女と見られている不如意を、 心ならずも味わい続ける毎日らしかった。」 「鷗外の末子の眼から」
「結婚したての頃、年末になって、実家の母親がきちんと茉莉が役に立っているか、 婚家にたずねていったところ、当の本人は羽根つきをしていた。 それを知った母親は、うなだれて帰ったという。」
群ようこ「贅沢貧乏のマリヤ」
|
|
「どこの奥さんでも出かけるが、夫が帰るまでには帰っていて 夕食の支度もするし子供の宿題も見終わっている。 それならば差し支えはないが、出たら最後何時になるかわからない。
その間夫と子供を忘れている。家があるのを忘れている。 義兄がそれを嫌がって怒った勢いで「一日座ってろ」と言ったのであろう。
茉莉は出かけたら適当な時間に帰るということができないから出かけないようにした。 すると出かけるのが面倒になって、終いには立ち上がるのも嫌になった。
食べて座っているうちにすいぶん太った。 庭を見ると芝生一面が犬の糞である。 犬は外へ連れ出す者がないので、運動不足から動けなくなっている。 小鳥は菜をもらわずに死んだ。」
「森鷗外の子供たち」
|
|
(最初の離婚に伴って実家に帰った茉莉と同居して)
「茉莉が帰ってからまず驚いたのは夜更かしである・・・ 朝がまた遅い。 卑屈になれないタチなので堂々と眠っている ・・・
茉莉が立ち上がって朝御飯に出る頃にはもう誰もいない。 茉莉だけはすることがない。」
「できるだけ寝坊をして、お昼すぎまで化粧をして、盛装して三越や銀座に行く。
「嫌らしい爺さんに限って、あたしを興味ある目で見るから不愉快さ」 「姉さんが太っているから嫌なジイさんが妙な興味で見るんだよ」
僕は茉莉を愛している。愛してはいるが、することなすこと気に入らない。 あんな奥さんをもらったら二日と一緒に住めはしない。 そう思うと山田の義兄がかわいそうになった。」
「茉莉は人と共同生活ができない人なので、 親兄弟でも一つ屋根の下に住むことは落ち着かず重荷で苦しかった。
母は自分が生んだ娘の重さに耐えがたくなると、 茉莉を見据えて「大荷物」といった。」
「森鷗外の子供たち」
|
本人の談
|
「(少女時代)平常の私は朝起きてから、夜床につくまで何もしなかった。
朝、女中のいる方へ行って、大きな声で 「顔あらうお湯」 というだけのお嬢様であった。
「かおあらうおゆ!!!」 と私がのたまうと女中がそれを捧げ持ってきた。
そこで、資生堂石鹸で顔を洗い・・・髪洗いの時には盥(たらい)の中に 湯を湛えた洗面器(銅(あか)の)の上へ頭を突き出して、 女中が襷(たすき)がけで洗った。」
森茉莉全集7 「昔と今の少女たち」
|
現代でも全く色あせない筋金入りの厄介人、 ダメウイメンズ筆頭。
まして当時の女性観や地方都市の秩序性の中ではあまりにも破天荒、
森茉莉砲の破壊力はぶっ飛んで突き抜けていたのだろう。
大瀧詠一「君は天然色」
森茉莉「君は天然」
当時「超弩級の家事無能力」
今なら「超DQNの家事ネグレクト」・・・
|
「茉莉が三度目の上京をした時も出むかえたのは僕であった。
汽車からおり立ったのは姉と、十六七になる博士の甥と先妻の子どもである。 ・・・当然うちへ来るものと思っていると、どこからともなく博士の姉が現れて 自分の子であるその少年と、子どもを連れ去ってしまった。
残された二人は、その場から予定されていた芝居に行き、夜ふけになって家に帰った。」
「翌朝茉莉が電話をかけると、いずれ仲人と挨拶に行くと、ていねいな返事があった。
へんだと思いながら気にとめずにいると、二日後に仲人の夫人が来た。 玄関で「少々お待ちください。」と言ったのに、夫人はだまって上がってきた。
用件は離縁の通告であった。
東京の里へ帰って芝居を見ておいでと言われ、何も知らない茉莉は仙台から 6時間汽車に揺られて戻ったのである。
そう思うと、激しい怒りで声が出なくなった。」
「・・・ことの折衝にあたる母の苦痛は言語に絶した。
先方が離婚を決意した理由には堂々たるものがあって、 「恐れ入ります、ごもっともでございます」をくり返すほかはない。」
「理由のあらましは、茉莉の散歩にあった。
毎日の市中見物を禁止されると、仙台には銀座がない、三越もないという不平となった。
博士は仙台市の名士であるが、三越の本店に移転を命ずる権力も財力もない。 それほど東京がよければお帰りくださいという結果になった。」
「・・・こんどは、さすがの茉莉もまいって、 奥の床の間にくずれるように寄りかかると、魂の抜けたうつろな目を一点に据え、 しゃっくりとも溜息ともつかない声を発して食事もせず、 散歩もやめて閉じこもっている」
「鷗外の子供たち」
|
森茉莉は佐藤彰との破局を予感していたのか。
弟・森類の
「東京に遊びに行っておいでと出されたまま仲人から離縁を言い渡された」
が実際のいきさつに即したものであるならば、
茉莉にとっては全くの不意打ちで夫から突然に、
究極の拒絶を突き付けられたことになる。
「新潮」編集者で、森茉莉と30年近い交流があった小島千加子の述懐。
|
小島 あの再婚で、茉莉さんは敗北を味わったと思うの。 間違いなく人生の敗北を味わったのよ、あの再婚は。
―茉莉本人から仙台時代の思い出をお聞きになったことは?
小島 一言も言わないですよ、茉莉さんは。 私も後で知って「え?そんなことがあったんだ」って思ったくらい。
小島 ・・・完全に抹殺した。それだけ自分には堪えたんですかね、 表面は笑ってるけど。
あまりにもつまらなかったという結論だったのか、なんだかよくわかりませんけど。
インタビュー「編集者から見た不思議な作家の素顔」小島千加子 文藝別冊「総特集 森茉莉」所収
|
茉莉と佐藤家の確執が傾斜を強め亀裂を深くしていく中で、
佐藤彰がどのような立場、どのような態度であったのかは知るすべもない。
主導権は別のところにあり、彼も妻に対して最後まで離別の決定的な態度を
見せなかったということなのだろうか。
|
「親の頭の中には茉莉の離縁があるが、 離縁そのものよりも、 だまされて上京させられたことの方が身にこたえている。
先方が悪いならば、抗議の申しこみようもあるが、 こっちが悪いのだから、非難はできない。 幾度繰り返しても考えはそこで止まった。」
「森鴎外の子供たち」
|
仙台からの手紙3
|
「一番いゝ方法は訳をするか小説を書くかしてお金を取ることです。 ・・・その点自分の好む芸術で立派に収入を得られるマリ姉さんを、私はつくづく羨む。」 8月23日 杏奴から茉莉
「細君がただ単に女として(肉体だけでなく精神的にもではむろんであるが、つまり女としてだ)愛されてゐるという事は侮辱だ。 細君としてどっしりとこの家に存在してゐるのでなくては不愉快だ」
「佐藤家といふ輪の中では、私は無産者だ。プロレタリアが反旗を翻しているのだ」 9月11日 茉莉から杏奴
「女にヒステリーが多いといふのは決して女の不名誉ではない。 若し男が現在の女のやうに自由がなく、妻一人に愛してもらはねば 誰からも愛される事の出来ぬ境遇になったら、 全世界の男といふ男は猛烈なヒステリーになって その発作のために殺人、自殺、十人斬りは到る所で行はれ、 世界は暗黒になるだらうよ。」
「全世界の女は今、仕事をどんどんするより外はないのだ。 ヒステリーに多少なるのは止むを得ぬ。 細君は夫のためにヒステリーになり、女は恋人のためにヒステリーにとなる。 多少ヒステリーとなるのはやむを得ないが、 仕事といふものがあれば発狂するまでにヒステリーを昂じさせなくてすむ。 仕事だ。仕事だ。」
「はけ口をこしらへなければならない。 はけ口は仕事ばかりでは駄目だ。 許された範囲で享楽を求めなければならぬ。」 以上9月15日 茉莉から杏奴
「では勉強をするからね」 9月20日 茉莉から杏奴
「あゝ杏奴よ、勉強をしようね」 9月21日 茉莉から杏奴
「では明日は勉強するぞよ。」 9月22日 茉莉から杏奴
「人間はいつかは死ななくてはならないのですね。一日も惜しんで仕事をしませう。」
12月2日 茉莉から杏奴
|
森茉莉は、公表されている略年譜によれば、
再婚の前年の昭和4年には雑誌に翻訳の連載を始めていて、
翌昭和5年にもモーパッサンの翻訳を連載している。
一連の言葉は、彼女の佐藤家の中での経済的・精神的な自立に向けた抱負を
率直に示すものだっただろう。
夫・佐藤彰の研究に苦闘する妥協のない態度にも触発されながら彼女が描いた、
仙台での新生活への希望の吐露でもあったと思われる。
だが、そうした努力はかえって彼女を一層困難な立場に追い込んでいく。
「遊んでばりゐる奴だから、あなた達(先妻の娘二人)もそんな馬鹿にならないやうに」
「女は針が第一だ」
「学者といふのなら旗を立てて屋根の上にでものぼってゐろ」
(1月19日付け手紙の中で茉莉が伝える義母の言葉)
義母は、東北帝国大学教授として名声、業績輝かしい愛息の嫁となった茉莉に、
人一倍の良妻賢母として振る舞うことを求めただろうし、
それは妻が無能力者とされ、選挙権や財産権も否定されていた当時の世相の中では、
圧倒的に正当性を得た態度でもあったのだろう。
が、「女は針が第一」と言われても、森茉莉は実の弟から先天性主婦失格症と称され、
戦後の世田谷でのアパート住まいを描いた自伝的小説「贅沢貧乏」の中で、
セーターやカーデガンに穴が開くとつづれないので、
深夜ひそかに新聞紙に包んでアパート近くの川べりに運び、
相当な量を捨てて沈めた、
と告白してしまう人である。
「あんな奥さんをもらったら二日と一緒には住めない。
そう思うと(茉莉の初婚の相手で離婚した)山田の義兄がかわいそうになった(森類)」
森(佐藤)茉莉が自分に即して生きようとすることは、
そうした婚家とその周囲の市井の要請に完璧なほど背馳し、
異和と不適合を突出させていくことにほかならなかった。
なごり雪
「まだ甘い生活の内はいゐが、私なぞもその内少し東京へでも出ねばなるまい。
普通の夫婦生活になれば、仙台にはあまりに享楽機関がない。」
9月15日 茉莉から杏奴
当時の仙台でも歌舞伎座や、森茉莉が杏奴への手紙(※9月16、17日)で
チャアリー・チャップリンの映画が仙台に来たといって心踊らした帝国館のほか、
仙台座、森徳座などの劇場や映画館が勃興の時期を迎え、
市民に親しまれ賑わっていた筈である。
しかし、昭和5年当時の仙台の人口は19万、東京23区は207万。
(人口推移一覧~全都道府県市区町村~ http://demography.blog.fc2.com/blog-entry-7050.html)
首都東京とパリでの都会暮らしで育った茉莉の奔放な魂を棲息させるためには、
仙台は街の拡がりも自由度も文化や娯楽の集積度も
決定的に縦深性や密度が不足していたし、
仙台に歌舞伎座はあっても、彼女にとって東京・銀座の<あの>歌舞伎座とは
非なるものだったのだろう。
後年、太平洋戦争中に喜多方(福島県)に疎開していた時代についても
街がないことで死にそうに退屈したとか、喜多方の町は「街」ではないとか
毎日のようにとある喫茶店に通ってコーヒーを飲んでいたのが町の評判になり、
「森さんの姉様が毎日〇〇屋でコーヒーを飲んでいる」といわれたとか述懐している。
森茉莉全集7 「新宿のParisien(巴里ジャン)、街、風月の若夫人、邪宗門 他」
森茉莉は、仙台から戻って5,6年後に住んだ浅草の自由な雰囲気を
パリに通じるものとして愛し、
「浅草の空は青く、自由の空である」(贅沢貧乏)と書く。
仙台の空は彼女にとってついにそのようにはなり得なかった。


|
仙台駅 |
| 牛タンブルース |
|
宮城野原1New |
|
宮城野原2New |
|
宮城野原3New |
| 連坊駅 |
| 法運寺 浮気封じの御岩稲荷 |
| 薬師堂駅 |
| 駱駝と瓢箪と白山神社 |
| 卸町駅 |
|
六丁の目駅 |
| 沿線を離れて・・・ |
| 案内の湯豆腐1 |
| 案内の湯豆腐2 |
| 車両基地 |
| 沢村対全米軍」1 快投 |
| 「沢村対全米軍」2 力投 |
| 「沢村対全米軍」3 熱投 |
| 「沢村対全米軍」4 奮投そして・・・ |
| 元祖二刀流・野球の神様ベーブ・ルース |
| 明日のジョーと仙台 |