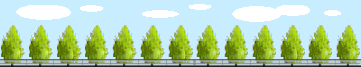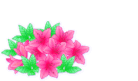森茉莉6 茉莉リン・モンロー・ノー・リターン
色ガラスの人
このホームページのタイトルは尾形亀之助の処女詩集「色ガラスの街」に
ちなんでいるが、森茉莉もまたある意味<色ガラスの人>といっていい。
|
巴里は春だった。昏い、靑い、空だった。 マロニエの並木は藻(うみのくさ)のやうに透って 灰色の街の谷間に、燃え上ってゐた。
・・・巴里の夜は深かった。深い、甘い、夜だった。鋪道に流れてゐる 珈琲店(キャフェ)の燈火(あかり)と、瓦斯燈の光しかない サン・ミッシェルの裏通り。
・・・雨に濡れた闇の中に、ダイヤモンドのやうに耀く珈琲店を見ながら、 古代の洋燈(ランプ)、帝政時代の繪本なぞが 飾窓の中に埃を被(かむ)ってゐる、眞晝の鋪道の上で、私は巴里に浸ってゐた。
刺(父の帽子)
|

|
≪イルミネエション ≫と、その夜も、次の日も、私は繰返して呟いた。 ≪おまりはイルミネエションが好きだなあ≫ と父が言って、笑った。
ダイヤモンド、紅玉(ルビイ)、靑石(サファィア)、 エメラルドの耀き、金の指環の光、 それらは月の光、雨の耀き、色硝子の光、瓦斯燈の光芒の美しさと、變りがない。
生活の中の美しさ、そこにも光と色は溢れてゐた。
空と花の生活(父の帽子)
|
|
ところでアネモオヌが、硝子戸を透(とお)す薄暮の光の中に、 今いったようなようすで浮き上がっているのだが・・・(中略)。
アネモオヌの色は、魔利を古い時代の西欧の家に誘(いざな)ってゆき、
花の向こうの銀色の鍋(なべ)、ヴェルモットの空壜の薄青、 葡萄酒(ぶどうしゅ)の壜の薄白い透明、 白い陶器の花瓶(かびん)の縁(へり)に止まって チラチラと燃えている燈火の滴(しずく)、
それらの色は夢よりも弱く、幻よりも薄い、色というものの影のようにさえ、思われる。
(贅沢貧乏)
|

(いわゆるひとつの、アネモウヌ)
この人の色彩感覚は、光のスペクトルを析出させるプリズムのように
あふれる色相と彩度の世界を描き出して飽きないものがある。
とりわけ光と闇の混交と散在、
昼と夜の静かな遷移や満ち引きを背景にして
その感性が印象的に姿を現していると思える。
それは、ロウソクやランプやガス燈や白熱球の灯の、
ほの明るくまたほの暗い、
それ自身の中に夜の原形質を潜ませているような
光源の揺らぎや煌めきを受けて浮かび上がるもの。
あるいはガラスを透過する光の入射角や
屈折の徐々の変移の中で
昼と夜の汽水域のざわめきや次第に傾きを増す日暮れの気配に感応するもの、
とでもいうべきだろうか。
現代の、光の塗料で夜の闇を塗りつぶし
揺るぎない昼の明晰性を現出させるようなLEDや
蛍光灯の照明の中で次第に減衰してしまった、
初源の感受性のようなものを感じて心に残る部分である。

そしてまた、森茉莉が父母と過ごした時代の記憶に言及する場面で、
しばしばこの人の中で自我が静かに白熱化するのが
感じられるときがある。
そこでは、森茉莉自身が防御なしで言葉の最前面に
身を乗り出し情感を疾走させている。
物語の遠景もまた交錯する追憶の光と影を受けて昇華し、
鮮やかに彩られている場所である。
|
提灯を大切さうに、ゆっくりと延ばすとほろほろと紙が鳴って、 すぐに提灯に描かれた舟や漁夫、焚松(たいまつ)なぞの繪が蠟燭の炎を中心に、 美しく浮かび上がった。
・・・橙(だいだい)色の岐阜提灯は少しの風にもゆれ、庭の闇の濃くなるに つれていよいよ紅みを增して美しい光りの暈(かさ)を、つくるのだった。
「幼い日々」(父の帽子) ※夏の夜、父が生家の提灯に火をともす場面
|
|
日が暮れかかり、もうそこここに灯(ひ)の點(つ)き始めた淺草の 仲見世の石疊を、私は母に手をひかれて歩いてゐた。
・・・兩側の店の中はもう金色に明るく、人形や、金平糖(こんぺいたう)の 瓶(びん)、赤や靑のポンチ繪の本なぞが、隙間なく並んで輝いてゐる。 店の中が明るくなればなるほど夕闇は深くなっていった。
同上
|
|
廣い家の丁度中庭にある、四疊半で二人は食事をした。 綠の溢れる庭の木々には、夏の氣配が濃くなってきてゐた。
どこやらに死の影が感ぜられる、庭の小蔭や部屋のすみの暗がりが、 母には恐ろしかった。
父の痩せた手に支へられた象牙の箸が、白い砂糖の陰に透るうす綠の梅を、 薄赤い杏子(あんず)を、崩していった。
「父の死と母、その周囲」(父の帽子)
|
森茉莉の「半日」は、父・森鴎外がしげ夫人と実母峰子の軋轢を描いた
自伝的小説「半日」について述べたエッセイ。
鷗外の「半日」では、明治天皇の先帝・孝明天皇の霊祭の日の朝、
宮中参内の支度をする主人公高山博士の前で、妻の母に対する鬱積した不満の
噴出が始まり、夫婦は険悪な雰囲気に包まれる。
博士は大祭出席を取りやめて、妻を諫め、さまざまに苦言を続ける。
そうした夫婦の会話と博士のめぐらす思索の中で半日が過ぎていく。
作品中には森茉莉を投影した博士の娘「玉」も描かれている。
作品の中で高山博士は全面的に母親にくみし、
夫人に対し延々と批判と諫言を述べていくのだが、
実際の鷗外の執筆動機も、家庭内のいざこざを赤裸々に作品化・公表する
ことでしげ夫人のヒステリーを牽制し、
夫人を母に謝罪させようとしたものとされているようである。
◆森茉莉の「半日」は、父の小説に対して、
自身の幼少時の記憶や観察をもとに、母を庇い、
ある事件をもとに変化した家族の関係に触れていく。
幼い茉莉が百日咳で重体となり
医師から余命一日の宣告を受けた時に、
呼吸困難の苦しみから解放するため、
安楽死が実行される寸前までに至ったのである。。
それ<安楽死>を最初に医師に諮ったのが祖母(峰子)だという。
安楽死はたまたま入室して来た、しげの父(鷗外の義父)によって
制止されるが、その記憶は鷗外の中に滓(おり)のように残り
峰子との距離を微妙なものに遠ざけ、しげとの融和をもたらす。
(鷗外にとってその激しい葛藤の記憶が「高瀬舟」執筆の契機とも
なったという。)
茉莉は父の小説「半日」と「金毘羅」を取り上げ、
その時の経緯と父母の苦衷を書き記している。
ここでの茉莉は白熱化する自我が切々と心情を吐露していく。
表出された言葉は美しく哀しく父母への敬愛に満ちていて、
父鴎外の「半日」を超えて強く心をひき付けるものがある※。
※鷗外の「半日」の高山博士は、多分に鷗外自身が投影された要素が
強いとされている。
博士は息子として全面的に母親側の立場に理解を示していて、
代弁者のように振る舞っている感のある部分も少なくない。
そのあたりは半ば<エネミー夫>的なダークサイドに落ちているようでもあるが、
一方では、宮中の大祭出席の用務を躊躇なくキャンセルして
夫人との対話に臨み、嫁姑の決定的な破局をきわどく防いでいく。
夫人の直情的な訴えを理詰めで分析し、諫(いさ)め、淡々と説き伏せていく場面に
家長(でもあり夫でもあり息子でもある大人の男)として、
細心の注意を払い、労をいとわずに家族間の舵取りをしようとする
鷗外の意識が、特徴的に現われているように思われる。
それは、鷗外が夫人と母の確執や夫婦間の軋轢に対して、苦々しくもビビッドな
問題意識を持って向き合い、対処しようとしたことを意味するものでもあるだろう。
また、それらを単に日常性の中の卑小な些事として置き捨てず、
現在の切実な課題としてすくい上げ、作品に再構成しようとする、
作家・鷗外の意識を見ることもできるかもしれない。
|
唯「半日」といふ小説だけのために、「親類」といふ、 何處の家でも兎角嫉(ねた)み、反目、小競合(こぜりあ)ひ等の塊である一群の、 母に對する批難が正當化される事に対しては、落膽しない譯には行かない。
・・・私達は、父の小説の中の一つによって永遠に、 「狂人染みた女から生まれた系族」といふ感じを受け、 永遠にそれに纏(まつ)はられて生きて行かなくてはならない。
母の系統の遺兒の中の最年長者として、時には切(せつ)ない心持になる。
・・・・・・
「玉」である私は「半日」の發表に「苦情」は言はない。 この文章は言って見れば成長した「玉」の「博士」に對する、哀しい訴ヘである。
森茉莉「半日」
|
ここでは、父母への白熱化する情感が切々と伝わって心をうつ。
だがその一方で、森茉莉が後年のドッキリ・チャンネルで垣間見せた、
固陋とも思える断定と攻撃の激しさは、
皮肉なことに実際は「母の系統」よりも、
軍医・医学博士としての父のそれ※に重なるように感じられてしまう。
※いわゆる陸軍の「脚気惨害」事件の中で、軍医であり軍高官として渦中にあった鷗外の
責任について、ネット上でも、擁護と批判それぞれの立場から様々に言及されている。
多くは陸軍の脚気対策を拒んだ頑なな言動を厳しく批判するものであるが、事実関係の
具体的な考証が十分に示さないまま流布、拡散されている部分も感じられる。
ただ、ドイツ・コッホ研究所に学んだ鷗外が細菌原因説に立ち、海軍の兵食改革や
鈴木梅太郎の糠の有効成分の研究など栄養学的なアプローチに対し、
相当に辛辣で峻烈な批判を行ったのは事実のようである。
( 現在では、脚気の原因はビタミンB1の欠乏であることが明らかになっている。
当時は原因不明の病であったが、海軍は遠洋航海での比較実験を通じ、明治10年代
末には主食を白米からパン食、ついで麦飯に切り替え、脚気予防に大きな効果を上げて
いた。かの海軍カレーも、脚気対策として導入されたものだという。
しかし海軍側では脚気の原因をたんぱく質の不足であると主張したため、理論的にも
消化吸収実験等の結果からも反論を浴び、国内での賛同は得られなかった。
鈴木梅太郎は東京大学名誉教授(農学部出身)。脚気予防に有効な成分として、糠の
有効成分オリザニン(ビタミンB1)の抽出に成功する。
国立公文書館・発明のチカラ「オリザニン」 http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hatsumei/contents/51.html
他方、陸軍は主流だった細菌原因説から、事実として効果を上げていた海軍の兵食改革
を強く批判。
しかし、当時の戦地への輸送力の低さ等もあり、陸軍として積極的な脚気対策が講じら
れることがないまま、白米主食を継続する。
結果、日清・日露の両戦役などで膨大な脚気被害が発生した。)
日露戦争では、脚気によって陸軍で25万人が脚気患者となり11万人以上が戦地入院。
2万7千人以上が死亡する。
その実情の一端を、従軍した田山花袋が短編小説「一兵卒の死」で描いている。
海軍では(少なくても日露戦争においては)脚気被害は軽微であり、死亡者はなかった
とされている。
やはり森茉莉は、よくも悪くも、父・森鷗外の巨大な重力場からの照射の中で、
深い因果性に染められた人だったと思えるのである。

古山寛、ほんまりう「漱石事件簿」から引用


紫陽花の花の咲く頃
森茉莉は、様々な境遇の変化や屈折や挫折の悲哀をくぐり抜けてなお、
意気軒昂でひたむきな人だった。
その向陽性。光と影と色への豊かな感受性と表現。
奔放で自由な荒ぶる魂の棲息。
歯に衣を着せない(あるいは傍若無人の)批評と好悪の露出。
父鷗外とその時代への思慕の純粋性。
そうした様々な表情の中に多くの女性ファンをひきつける魅力が存在しているのだろう。
|
魔利は腰をかけたままで、花が吐き出す香気と、硝子(ガラス)の透明の 中にある誘惑的な、それはたぶん自分自身の中にあって、 探りあてたいという心持を、どこかで魔利(マリア)に起させているところの、 なにものかである、その誘惑的なものに取り巻かれながら、 贅沢費の払底を歎くのだが、 そんな日が幾日か続いた後には、再び歓喜の日が訪れる。
人間万事塞翁(さいおう)の馬。というのは真実(ほんとう)らしい。 ・・・魔利は心の中で笑い、新しいスカアトをはいて嬉々として、街へ出る。
贅沢貧乏
|
森茉莉の人生が終焉を迎えたのは1987年(昭和62年)6月。
その紫陽花の季節の頃、「世界の中心で、愛を叫ぶ」の中で主人公とヒロインに
初めての出会いが訪れる。



|
仙台駅 |
| 牛タンブルース |
|
宮城野原1New |
|
宮城野原2New |
|
宮城野原3New |
| 連坊駅 |
| 法運寺 浮気封じの御岩稲荷 |
| 薬師堂駅 |
| 駱駝と瓢箪と白山神社 |
| 卸町駅 |
|
六丁の目駅 |
| 沿線を離れて・・・ |
| 案内の湯豆腐1 |
| 案内の湯豆腐2 |
| 車両基地 |
| 沢村対全米軍」1 快投 |
| 「沢村対全米軍」2 力投 |
| 「沢村対全米軍」3 熱投 |
| 「沢村対全米軍」4 奮投そして・・・ |
| 元祖二刀流・野球の神様ベーブ・ルース |
| 明日のジョーと仙台 |